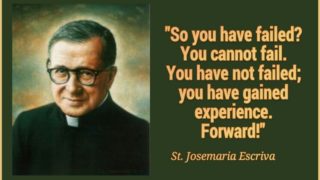ジョセフ・レイモンド・マドゥルガ神父
ムスキス神父がローマに戻って後、日本に行った最初のメンバーはジョセフ・レイモンド・マドゥルガ神父である。
彼こそ、エスクリバー神父にとって、自分の代わりとなるのに最適な人物だった。
ジョセフ・レイモンド・マドゥルガは、剛毅と忠実の人である。1922年、11月10日、スペイン、サラゴサに生まれ、17歳のとき、オプス・デイの信者になった。
22歳でアイルランドに単身留学し、かの国に初めてオプス・デイをもたらした。その後、司祭になり、アメリカに渡って地域代理を務めている。
彼が日本に来ることになった逸話は面白い。
ホセ・ルイス・ムスキス神父は、日本からアメリカのシカゴに帰ると、だんらんで旅行話をした。その時、漢字がたくさん書かれた紙を皆に見せて言った。
「これをどう思う」
もちろん、読める者は誰もいない。その意味不明の複雑な文字を見ただけで、日本が西欧諸国といかに異なる文化をもつ国か誰もが分かったし、日本での使徒職の困難を察することもできただろう。
その場にいたジョセフ・レイモンド・マドゥルガ神父は、その時言った自分の感想が、日本行きを方向づけるとは思いもしなかった。
その言葉は、彼のユーモアに富む屈強な性格をよく表している。
「面白いね。こんなものを勉強するのが義務になったら面白いよ」
この言葉は、後ほどローマにいるエスクリバー師に届いた。
エスクリバー師は、ジョセフ・レイモンド・マドゥルガを知りぬいていた。
彼にこそ、日本での宣教という長年の夢を託せる人物だと考えたのだろう。まもなく、マドゥルガに一枚の葉書が届いた。
それには、エスクリバー師とマドゥルガ神父の郷里であるスペイン、アラゴン地方のことわざだけが書かれていた。
「山を登るためには、ロバがほしい。下り坂なら、自分で登る」
日本に行ってくれ、など一言もない。
相手が嫌だったら断れるように、あくまでも相手の自由を尊重する。これが、エスクリバー師の頼み方だった。
ジョセフ・レイモンド・マドゥルガには、エスクリバー師のほのめかしだけで十分だった。
彼は即座に決心する。日本という険しい山を登るために、キリストを乗せて歩くロバになろうと。
最初のメンバーたちの来日
ジョセフ・レイモンド・マドゥルガ神父は、1958年11月8日に来日した。36歳だった。
しばらくは、大阪で田口大司教の客人となり、その後、紹介を得て、豊中市に住む大阪大学教授宮田氏から部屋を借りた。
当時、宮田教授を大変驚かせたことがある。マドゥルガ神父が滞在したわずかの期間に届いた郵便物の多さである。
毎日のように、ドサッと届いた。しかも、世界中の至るところからである。この人はきっと大変偉い人に違いないと、宮田教授は目を見張った。
実は、主の降誕前には、家族や友人にクリスマスカードを送る習慣がキリスト教国にはある。
エスクリバー師は、日本で孤軍奮闘するマドゥルガ神父のことを各国の子供たちに伝えていた。
世界中から届いた郵便物の山は、それに応えて、私たちは日本のために祈っていますよ、という励ましのメッセージだったのだ。
日本に行く前に、マドゥルガ神父はローマに寄って、エスクリバー師に会っている。
「一人で大丈夫か」
という問いに、マドゥルガ神父は答えた。
「心配いりません。私は雑草みたいなものですから」
エスクリバー師は、この時、三つのことを彼に言ったらしい。
一、なるべく早く次の神父を日本に迎えるように。
二、なるべく早く家を借りるように。
三、なるべく早く宗教法人の手続きをするように。
次の神父は、2月後の1959年1月18日に着いた。フェルナンド・アカソである。
アカソ神父は、ローマで長年エスクリバー師のすぐ傍らで過ごした人である。オプス・デイ属人区長ハビエル・エチェバリーアと共に、マドリッドからローマに留学し、常に同じ大学で同じ教科を学んできた。
後にアメリカに渡ったアカソ神父は、自分も日本に行きたいとエスクリバー師に手紙を書いていたのである。
この人によって大阪府豊中市にオプス・デイの最初のセンターが置かれた。1959年4月8日には、アジアにおけるオプス・デイ最初の聖櫃が置かれた。
同年、7月29日には、アメリカから人目の神父ホセ・アントニオ・アルミセンが着いた。アルミセン神父はスペイン、パンプローナ出身、ユーモアに富む愛と信仰の人である。
ちなみに、生まれたばかりの自分の甥に日本から書いた彼の手紙を、スペインで入手できた。面白いのでご紹介しよう。
「愛する愛するホセ・ハビエル、誕生日おめでとう!
ママといっしょにいてあったかいだろう。おいしいお乳ものんでいるだろう。
おまえが生まれて喜んでいる。すぐに洗礼を受けて嬉しいよ。おまえの両親は洗礼のすばらしさをよく分かっているね。
おまえは両親を愛さねばならない。天の御父も、御母マリアも愛するんだよ。守護の天使にもあいさつしなさい。彼はいつもおまえのそばにいるからね。
おじいちゃんも、おばあちゃんもおまえを愛している。言うまでもないが、もちろん日本にいる叔父もだ。
オプス・デイの創立者、ホセマリア・エスクリバーもおまえと同じ1月9日に生まれた。もしも神様がお望みなら、おまえにもオプス・デイの召し出しをくださるだろう。
オプス・デイの召し出しに応えることは、絶対に後悔しない。なぜなら、神様のみ前で偉大なことだからだ。
さあ、ホセ・ハビエル、よく寝て、自由な時間にママのお乳をたっぷり飲め。
おまえにたくさんのキスを送るよ。ホセ・アントニオより」
女子メンバーの来日
1960年6月13日、女子メンバー人が日本へ向かって出発した。船旅だった。
ローマを発つとき、創立者はセンターの回廊にかけてある聖母の絵の前に小さなランプを燈した。それは、旅の間、彼女たちの保護を聖母に願うためのものだった。
彼女たちが出発する前日、創立者は一晩中祈りをささげた。
その祈りの力強さを彼女たちは旅の間、感じることになる。
17日金曜日、船はポートサイドに寄港した。様々な人種の人々が織り成すざわめきの中で、マリア・テレサ・バルデスは思いがけず封筒を渡された。
差出人を見て、驚き、満面に笑みを浮かべて仲間のもとへ駆けていった。手紙はローマから届いたものである。
それには次のようなことが書いてあった。
「あなたがたが日本に着くまで、回廊を帳る人があなたがたを思い出し祈るように、マリア様のご絵の前に灯りを燈し続けてくださいと、パドレは言われ、私たちはそのようにしています」
6月27日、コロンボの巨大な港に着いた。そこにも、手紙が待っていた。
その後で、船は中国の海に舳先を向けた。
長い海の旅が続く。

見渡せば、遠く天と地をつなぐかのような水平線が広がっている。
船風を受けながら、マーガレット・トラバースはその年のご復活のごミサで言われた創立者の言葉を幾度となく思い出していた。
「剛毅をもって、確実に、喜んで、そして誠実であるように」
その言葉は、これから始まる40年以上の日本での生活を支えるものとなった。
7月15日、ようやく日本が見えてきた。
神戸港に着くと、黒い髪の毛、黒い瞳をもつおだやかな人の日本女性が待っていた。彼女たちは日本での最初の友人たちだった。
車で夙川という住宅地域に向かった。
アジアで最初の女子メンバーのセンターがそこにあった。庭には松や桜の木が見える。門の上に「夙川スクール」という表札が輝いていた。
日本の文化を尊重し、日本の習慣に親しみ慣れる努力を続けること。
エスクリバー師が教えてくださったことを、実行していく日々が始まった。
ロンドンからの電話
1960年の夏、日本に着いたばかりの彼女たちは、様々な困難に当惑していた。
慣れない生活習慣、難解でよく分からない言葉、進まない使徒職。一人一人の心に、疲労が蓄積してきた。
そのような時に、ロンドンから突然の長距離電話があった。
受話器をとったマリア・テレサ・バルデスは、パドレだと知るや耳を疑った。
パドレからの国際電話、それは例外中の例外だった。当時、パドレとの通信は、普通、手紙が原則であった。
手紙は時間がかかるが、メッセージを熟慮した上で正確に伝える手段としては適していたからある。
それに、当時の国際電話には大変な お金がかかった。メンバーが電車代やタバコ代を切り詰めてまで、お金を節約していた時代である。国際電話を使うことは、まずなかった。
清貧のうちに生活していた師が、そのお金を捻出するために長い間他の出費を押さえていたことは、後で知られることになる。

「ロンドンから電話をしています。この短い時間をよく活用しましょう。一人一人と話したいのですが、できますか」
師の声は熱くて心がこもっていた。
「はい、パドレ、では他の姉妹に変わります」
バルデスが他の姉妹を呼んで受話器を渡すや、すぐに師の声が聞こえてきた。
「あなたは、誰ですか?」
「マーガレットです」
「マーガレット、あなたは幸せですか?」
彼女たちは皆、同じように尋ねられ、図らずも同じように答えた。
「はい、とても幸せです。パドレ」
エスクリバー師は言った。
「神様はあなたを祝福していますよ」
パドレの言葉は、彼女たちの心を元気づけ奮いたたせた。
たとえ遠く離れていようとも、パドレは父親であり、私たち子供一人一人を思い、愛していてくださる。あふれるものを抑えきれず、幾人もが泣いた。
数日後、日本から届いた手紙には書いてあった。
「あの電話がまったく予期していなかったものだけに、とても驚きました。しかし、それは正に私たちが一番必要としていた時でした」