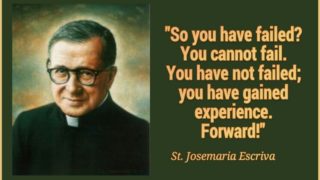もし自分の命が残りわずかだと知らされたらどう振舞うでしょうか。
黒澤明監督の映画に「生きる」という名作があります。
役所に勤める老年の男性が不治の病を知らされ、残り半年の命をどのように生きたかを描いた作品です。
映画「生きる」の前半より
自分の余命が短いことを知った主人公は、それまでの味けない判で押したような生き方に疑問を持ちはじめ、悩みます。
そして、自分が心底生き甲斐を持ってできることを探しさまようのです。
見知らぬ小説家と知り合って夜の歓楽街にも案内されますが、空しさが残るばかりです。役所を無断欠勤して、生の意味を求めてさまよう日々が続きます。
そしてある日、役所の同じ課にいた女子職員が、新たな生き甲斐を求めて玩具工場に転職したことを知ったとき、彼は悟ります。
他人のためになる仕事に没頭することこそ苦悩を越える道であると。
意外にもそれは、これまで味けないと思っていた役所の仕事の中にありました。
彼が選んだその仕事は、町に小さな公園を造るという平凡なものでした。ところが彼は、人がかわったように、その仕事に打ち込み始めます。
誠心誠意働き、多くの困難にもひるまず、遂にその仕事を成し遂げるのです。
余命を知らされてから半年後、完成した公園のブランコにゆられながら、彼は微笑みをもってその生涯を閉じるのです。
映画「生きる」の後半より
その生き方は、彼を知る多くの者を驚かせ感動させます。
なぜ、彼はかわったのか。なぜ、彼はこれまで注意を払いもしなかった仕事に、全力を傾け、命を燃やすように打ち込むことができたのか。
余命を宣告されるまでの彼の長い緩慢な生活ぶりを知る者にとっては、それは大きな驚きであり、疑問でもありました。
映画「生きる」の後半部分は、お通夜の席で参席者たちが生前の主人公を回想する場面になっています。
彼らは、主人公のあの半年間の生き方に感動し、「よし、明日からは自分たちも彼のようになろう」と堅く誓い合います。
しかし、一夜明けると、彼らは普段のだらりとした生活に戻ってしまうのです。
私はこの映画を通して、余命時間を宣告された人の「生きる」姿勢の変化にまず驚かされました。
人は自分の命がわずかだと知らされたとき、こんなにも「生きる」ことを真剣に考え、行動するようになるのです。
本当に価値のあるものを追い求め、そのために残り時間のすべてを捧げ尽くすようになるのだとこの映画は語ります。
ならば、私をも含めて自分の残り時間を意識しない多くの人々は、その人生を真剣に生きていないのかもしれません。
映画の後半部分は、そんな私たちの一面をお通夜の参列者の姿を通して見せてくれるようです。
平々凡々と生きて、それを悔いるが改めはしないあの参列者たちは、私たち普通の人間の姿を描いています。
もっと充実して生きたいとは願いつつも、実生活に戻ると力を出せないでいるのが私たちの現実の姿なのかもしれません。
人生のゴールを意識して生きる
度々、「死」を考えるのは良いことだ言われます。
幸い、カトリック信者にとって、死はとりわけ悲しいことではありません。この世での使命を終え、やっと天国へ行けると考えるなら、楽しみにもなってきます。
しかし、仮に自分があと半年しか生きられないと宣告されたら、どのように生きるのでしょうか。このままで天国に行けると確信でできるしょうか。
十一月は、カトリックでは死者の月です。亡くなった方のために祈る三十日でもありますが、自分の死と死に向かう生を考える時間でもあるのです。